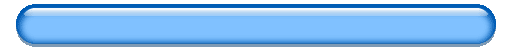
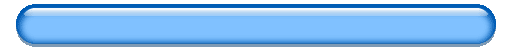
心の戦士心得、どのように支えていけるか
障害とは!
人の中に障害があるのであって、障害の中に人があるのではありません。生活という観点で見たとき、買い物に行くとか、身の回りの世話をする、人とコミュニケーションするとかいった日常の生活での行為自体が障害となるのです。わたしたちにはなんでもないことがつらいことになるのです。だからもうただ生活をする、それだけでも十分頑張っているのです。それを理解しましょう。
症状はその人のストーリー
ひとりひとり症状は違います。そしてそれぞれの
症状がその人のストーリーなのです。
だからそのストーリーに耳を傾けること
それこそ一番の支えです。
決まった法則はありません。
これが正しい生き方という決まった
ものがないのと同じでこれが正しい
支え方というのはありません。
ひとりひとりのストーリーに
耳を傾けて
ください。
そこに
道があります。
100人に100種のアプローチ
ひとりひとり違います。教科書はありません耳を傾ける。聞いて、聞いて、聞いて、また聞く。鍵はunderstand!その人の下手から、その人のリラックスした姿勢や場所で。無理やりでなく、その人の口からこぼれるように!たった一言でもいいのです。
その人を理解し、受容してあげてください。ゆっくり耳を傾け、受けとめ、観察してどんな障害(生活障害)を持っているのかを理解してあげてください。それは机に座り、面と向かって「悩みを話して・・・」ではうまくいきません。その人がリラックスして話したいときに話せるように場を持っていってあげましょう。そのためにあなたは監督、役者となるのです。その姿勢は高いところから「聞いてやるよ」ではなく下から、下に立って「聞かせて」understandそのものです。この理解しようとする姿勢が心にふれて、この人はわたしのことをわかってくれようとしているなと感じてくれたら成功の一歩です。それが愛がその人に通じたことです。
⇒わたしは「こんなことで苦労して、大変だ」といってこれるようになったらOKです。
⇒そのためにじっくりと耳を傾けてあげてください。聞く・・・です。そしてそれはものすごいエネルギーを使います。ですからあなたも消耗しないように!この人は聞いていると思ってもらうことが大切です。
☆しかし完全な理解は不可能です。それを自分に求めてはいけません。あくまでも聞いているよという姿勢が大切です。
その場面に入ったらあなたはその場面の仮面をつけるのです。その人が望んでいる役の仮面をつけてあげるのです。それは偽りではありません。
寝そべって話したいなら、あなたもそのようにあわせましょう。相手の望む役が何か、その人の症状のヒストリーから考えて見ましょう。
リカバリーとは!
「自分たちが求めるものは病気からの回復ではなく、人々の偏見、医療による傷つき、自己決定の欠如、働いていないことを否定的に見られること、壊された夢などからの回復である。」・・・ディーガン女史
当事者理解のための参考事項!
障害の意味
幻聴、幻覚、妄想などの疾患があると、買い物へ行くということが難しくなります。バス停で誰かが話しかけてくる声が聞こえる、誰かが見ているのでは、・・・・そのために生活のひとこまの、なんでもない「買い物とかバスにのるといった行為」がその人にとって「障害」そのものとなるのです。それが生活障害です。人の中に障害があるのです。障害の中に人がいるのではありません。障害者という人種があるのではありません。障害者もひとりの人間です。健康だけれど肢体の不自由があるという障害と同じで、普段の生活の中でうまく動かせない心の働きの障害があるのです。
陽性症状というわれる幻聴、幻覚、妄想、あばれるは薬で抑えられ、そう厄介なものではありません。その後に現れる陰性症状といわれる感情鈍化、無気力などの症状は普段の生活で、部屋の掃除をしない、生理整頓できないなどの、生活が退化する生活障害になります。陽性症状の後に現れる陰性症状が無気力、無感情、無反応や引きこもりなど、回復に時間を要する障害です。できる限り陰性症状は抑えたいものです。
幻聴、幻覚、妄想
幻聴はブラックボックス内に2日間いれば誰にでも起きるという実験結果があります。彼らは精神的なブラックボックスの中にいるのです。そのブラックボックスから出してあげるのは容易なことではありません。その人のストレスの元に近づけは、幻聴、幻覚、妄想は強まります。それから遠ざかれば弱まります。良くその人を観察して、なにがストレスの元になっているかさっしてあげましょう。愛は見えないものを見る力をもたらしてくれます。understandその姿勢をとれば自然と愛は心にわきあがります。幻聴は会話形式なので、「もう話すな」「聞きたくない」と、その人が突き放すことができるよになるなら、消えて行きます。自分と幻聴とは別々と意識できるようになればしめたものです。その気付きが来るように祈り、そして、いろいろ試してみましょう。それはその人の気付きから来るものをです。決して説得、説明からはきません。それが異様なことでなく、その人の個性的なものだと知らせてあげることができたら、誰でも聞いていたり見ているものでなく、自分だけに聞こえ見えるものだと気が付けます。
そしてユーモアこそ鍵です。たとえば幽霊が見える。「そんなのいないよ」といったら、そこで終わりです。「そうなのわたしには見えないけどすごいね。」「そんなにいるなら皆集めてパーティーできるね」とユーモアで深刻さを薄めてあげましょう。幻聴、幻覚、妄想は決して暗いものばかりとは限りません。しかしたとえ、美しい女性とか、天国などの良いものでも幻聴、幻覚、妄想はいいものではありません。どちらにしてもとても辛いものです。
当人がリラックスした雰囲気で、ぼそぼそとそういう話しをしてくれる、それで十分です。それに対して、びっくりしたり、否定的態度を取らないことです。肯定的にうけとめ、うまく流してあげましょう。そのためにそれを疾患としてみるのではなく障害として見てあげましょう。
脱感作(だつかんさ)
これがリハビリの目的です。
たとえば買い物にいけない!それはまわりの人から何をされるかわからない。誰かが見ている。そういった恐れが元です。それでも買い物に一緒に連れて行くうちに、場所にもなれ、そして自分が思ったようでもないなとなれてくると、スーパーのどこに何があるかもわかるようになり、ひとりで歩きまわれるようになれます。それが脱感作です。つまり怖さがとれたのです。そのためにはゆっくりと行くことです。海で一度おぼれ恐怖を知った子ども、その子を恐れるなと水の中に突き落としたりはしません。母親が一緒に水際からほどよく離れたところに座り、子どもと楽しく会話する、そして次はもう少し近くで、そしてだんだん近づき、そして水際で話が出来るようになり、そして子どもが自分から水際で水遊びできるようになり、そして母親はその子を水際においてひとり遊びさせ、そして少しづつ子どもから離れて行きます。子どもは水際でひとり水遊びができるよになり、そして向うで自分を見ている母親を見て、安心するのです。その時子どもの心から怖い気持ちは消えています。これが脱感作です。そしてこれがリハビリの目的です。これが生活障害の脱感作です。そしてそれが愛です。信頼と信仰、そして希望を心に植えてあげることができたら愛が勝利します。その人が自分に自信を持てるようになるのです。自分もできる、何も怖くないじゃないか。それが信仰です。それは外からのものでなく、内からのものです。しっかりと心の中に刻み込まれた確信です。この信仰、確信が成長していけば脱感作ができあがります。
健康の公式 = 障害 分子
健康 分母
★リハビリ、または回復するとはどんなことでしょうか。どうしても障害がなくすことだけを考えます。健康=障害がゼロです。しかしそれが答えでしょうか?それである人が上にある公式を考えました。人の中の障害が分子です。そしてその人の健康、そして長所、良いところが分母です。どうしてもこの障害を抑えて小さくすることばかり、誰しも考えがちですが、治療によって障害を小さくすること、そしてもう一つ分母である健康或いは長所、良いところをのばすことで、生活が改善することができます。
障害を小さくするのに、薬物療法、精神療法、家族療法があります。
そして分母の健康、良いところ、長所は何でしょう。そこを伸ばしてあげることで、社会参加していけることになります。それはその人の潜在能力(Capability)を探って行くことからです。
潜在能力を伸ばし、障害を小さくしていくことで、辛さの数字は限りなく小さくなります。
そのためには当事者に共感しそして傾聴することです。これは共同作業です。二人三脚で行くことで、信頼と希望が生まれます。それは即座の結果を見ることはありません。時間がかかります。しかしその共感し、そして耳を傾け、ありのままを受け入れ、互いに道を探る作業をしていく中で、何かが起こります。それがきっかけとなり、分母の「健康」を膨らませ、たとえ障害があったとしても生活のしずらさが、軽減されていきます。その共同作業がリハビリそのものです。
どうしても障害を小さくすることばかり考え、症状を消すために薬に頼ることになります。しかしそれは健全なことではありません。障害があってもいいのです。それを共感し、そしてそばで支えてくれる人がいる。それが救いです。そして生活を長く続けられるように、改善していく方法をゆっくり見つけていく。それが大切です。これだという方法はありません。一人一人に一人一人の方法があります。それを見つけ探っていくのが、当事者と家族や仲間との共同作業です。「聞く」は自分の聞きたいことだけを聞くことです。だから聞きたくないことは門で閉じてしまいます。聴くは徳をもって心から耳を傾けることです。その人のありのままを、意見を言わず、聴いてあげることです。辛さを理解し、体感することはできませんが、それに耳を傾けてくれる誰かがいる。それはとても重荷を軽くしてくれます。とても難しいことですが、これがリハビリの秘訣です。ただ支える方がそれに飲み込まれてしまうことがあります。それは気を付けなければいけないことです。
![]()
現実に医師は毎日沢山の患者さんを相手にするので、カウンセリングに長い時間を割くのは難しいというのが実情です。より深い心のアプローチが必要な場合、カウンセリングを専門とする臨床心理士にカウンセリングを引き継いでもらうなどの工夫をしています。最近では医師のほかに臨床心理士がいる病院も増えてきています。
カウンセリングは、医師やカウンセラーが「心の鏡」となって、患者さんが自覚していない心の問題に気づいてもらい、自ら問題を克服できるように人間的な成長を促すことが目的です。患者さんのなかには、不安や悲しみ、怒りなど、自分の内面で起こっている心理葛藤に気づいていない人がいます。また、成長過程の環境や出来事によって、心にゆがみが生じたり、心に深い傷を負ったり、心が十分な成熟を遂げられないまま大人になってしまった人もいます。こうした心の問題が、過度のストレス状態を生み出し、心の病気を招いていることもあるのです。そこでカウンセリングでは、生い立ちから現在の生活に至るまで、患者さんからさまざまな話を聞きだします。そして最終的に、自分のどこに問題があるのか、それを解決するのはどうしたらよいのか、患者さんが自分で発見できるようにするのです。誤解しないでいただきたいのは、カウンセリングは人生相談ではないということです。悩みや問題を解決するにはどうしたらよいか、その答えを出すのはあくまでも当事者である患者さん本人です。医師やカウンセラーは、それを手助けする存在に過ぎないということを理解してください。
精神科医は、医学的診断や治療は行っても、患者さんに対する心のフォローアップが十分でなきないことがあります。もっと悩みをじっくり聞いてほしいと思っても、大勢の人が順番を待っている外来では、望めないことも多いでしょう。一方、いわゆるカウンセラーは、じっくり時間をかけて話を聞いてくれますが、病気の診断や薬の処方はできません。そのため、薬や他の治療が必要なケースでも、漫然とカウンセリングだけを続けて、病気の回復を妨げてしまう危険性があります。こうした危険を避けるには、カウンセリングルームなどを利用する場合でも、医師との連携が大切になります。
心身医学的治療法
1、一般内科ないし臨床各科の身体療法
2、生活指導
3、面接による心理療法(カウンセリングを含む)
4、薬物療法(向精神薬、漢方など)
5、ソーシャル・ケースワーク
6、自律訓練法、自己調整法、筋肉弛緩法
7、催眠療法
8、精神分析療法、交流分析
9、ゲシュタルト療法
10、ロゴセラピー
11、行動療法、バイオフィードバック療法
12、認知療法
13、家族療法
14、箱庭療法
15、作業療法、遊戯療法
16、バイオエナジェティックス療法(生体エネルギー療法)
17、読書療法
18、音楽療法
19、集団療法
20、バリント療法
21、絶食療法
22、東洋的療法
・森田療法
・内観療法
・針灸療法
・ヨーガ療法
・禅的療法
・気功法
23、神経ブロック療法
24、温泉療法
一部の紹介
■悪い習慣を変えていくための行動療法
人間のすべての行動は、生まれつきのものでなく、「学習」によって身についたものです。その考えに基づき、学習の誤りを修正して悪い習慣を変えていく実践的な方法による心理療法です。
▽誤った学習で身についた行動を修正して行く。
たとえば、パニック障害で「外出=パニック発作」という誤った学習をしたために、外出しようとすると不安に襲われて、「外出できない」という行動が身についてしまったと考えれます。そこで、この誤った学習を修正して、不安に感じることなく外出できるようにしていきます。脱感作で述べた例がその一例です。
■認知行動療法(認知療法)
・・・・認知のゆがみを修正していく
心身をとことん消耗してしまう人というのは、認知(物事のとらえ方)に、ゆがみがある場合が少なくありません。たとえば、うつ病の患者さんは、物事を何でも否定的・悲観的にとらえてしまう傾向があります。わかりやすい例を挙げると、あいさつをしたときに相手の態度がそっけなかったりすると、うつ病になる人は「私は嫌われているのだろうか」と、悪いほうに考えてしまいがちです。しかも、いったん考え出すと、どんどん思考はマイナス方向へと向かいます。そして憂うつになり、ますます悲観的な気分に陥ってしまうのです。
「認知行動療法(認知療法)」とは、こうした悪循環を断ち切るために、患者さんとの対話を通して、物事に対する思考のしかたを修正していこうとするものです。
▽認知のゆがみに気づくためには
たとえば、自分自身に次のように問いかけ、それに答えていく。その中で、自分の考え方のくせに気づき、他にもいろいろな考え方があることを知る。
①自分がそう考える根拠は何だろうか?はたしてそれは正しいのだろうか?
②別の視点から考えてみたらどうだろうか?他にどんな考え方があるだろうか?
③どの考え方がいちばん正しいだろうか?違う考え方を選んだらどうなるだろうか?どの考えのときがいちばん気分がいいだろうか?
■精神分析的療法
・・・・無意識の心の葛藤の原因を知る
自分が気づいていないだけで、心の中では不安や悲しみがうずまいていることもあります。こうした無意識の心の葛藤が、社会生活への適応を困難にしていたり、心身に症状をもたらす原因となっていることもあるのです。「精神分析的療法」は、面接の中で、患者さんの話について精神分析的な解釈を行い、無意識の心の葛藤を引き起こしている原因を探っていくものです。原因を知ることで心が軽くなり、それだけで病気が治る人もいます。
■森田療法
・・・・あるがままの自分を認める
神経症に用いられる心理療法です。神経症にかかりやすいタイプの人は、生への欲求や自己実現の欲求が人一倍高いという傾向があります。そのため、いったん心身の不調に注意が向くと、それにとらわれて、次第に病的な不安や恐怖に陥ってしまいやすいのです。そこで、症状をあるがままに受け入れて、症状があっても日常生活は普通に営めるということを指導していこうというのが森田療法です。
■音楽療法
・・・・音楽のリラクセーション効果を生かす
目的のひとつは、まず心身をリラックスさせることです。不眠などの症状を改善することです。さらに、音楽を通して、患者さんの心身の機能や心理状態をチェックし、それを分析することで、病気の背後にある心理的葛藤の解決に役立てることもあります。音楽を聞いたり、歌を歌ったり、楽器を演奏したりすることは、心を明るくし前向きにしたり、心身の機能をアップさせる効果もあるため、ストレス対処法としても利用できます。
■家族療法
・・・・家族システムのゆがみを改善する
心の病気が、家族関係に起因している場合は、医師と家族全員で話し合いの場を持つ「家族療法」が有効です。家族療法は、家族システム(家風や暗黙のルールを作り出す母体)のゆがみを、家族の方々に気づいてもらい、みんなで協力して問題解決に当たってもらうことが目的です。
■作業療法
絵画などの芸術的作業や、ゲームなどのレクレーション活動を通して、感情を発散させ、情緒の安定を図るものです。
◇かしこい患者になるために
治療を効果的に進めるためには患者さんの心がまえが大切になります。まず患者さんに心がけてほしいのは、向精神薬の作用や効果をよく理解したうえで使ってほしいということです。また薬に不安や疑問があったら医師を信頼して、処方した医師にすべて語ってください。心の病気に立ち向かうには、医師と患者さんが二人三脚で力をあわせることが必要です。(よい医師は話に耳を傾けてくれます。)また心理療法も医師まかせで効果が出るものではありません。患者さんが自分の抱えている悩みや問題を話すだけで元気を取り戻せる人もいます。必要なら薬の力を借りることで、症状を楽にすることもできます。しかし、それはあくまで症状を一時的に抑えているだけに過ぎません。ストレスに負けないよう、自分を変えていかないことには、根本的な治療にはならないのです。心理療法はそのための手段であり、医師やカウンセラーはそれを指導して回復の手助けをするに過ぎません。ストレス病を治すのは、最終的には患者さん自身でしかないのです。
![]() 時間と忍耐、そして沢山聞くことはエネルギーを要します。
時間と忍耐、そして沢山聞くことはエネルギーを要します。
生きる営みを取り戻すそのすべてがリハビリです。
そして人間としての自由を取り戻すことが回復です。
それは本人が自分から支援を求め、自分から克服したいと意欲をもてるように、支援できたら勝利は目の前です
家庭は大切なリハビリの場です。
楽しくゲームをやって笑っているときは幻聴、幻覚、妄想はありません。リハビリと意識しないで自然体で接しましょう。なぜなら生活のすべての体験そのものがリハビリだからです。
社会、地域の生活(暮らしの中に)にとけこんで、暮せるようになるのが最大のリハビリ・・・生活場面での回復となります。
作業療法
生きる営みすべてがリハビリテーションです。
引きこもっている人が、リハビリに行ってみようか、そして部屋の扉を開けて外に出ていくだけでもリハビリなのです。家から出て一歩、歩くことがリハビリなのです。
しかし家族でやさしくすること、カウンセリングすることは馴れ合いというのが邪魔してとてもむずかしいです。親子は親子でやり方があります。それをゆっくり見つけていきましょう。
⇒症状がストーリーと言いました。そのストーリーをゆっくりと読んでのみこんでいけば、おのずと方法が見えてきます。時間がかかります。
ひとりひとりの陽性陰性症状をそのためにじっくり時間をかけて観察しましょう。そこにこの人はこうだというパターンはありません。そしてマニュアルもありません。行動がそうだったから心の中もそうだということはありません。その人のヒストリーの中で、症状をやわらげ、健康、長所、良い点を伸ばす工夫を考えてください。
そのためにはただじっくり耳を傾け、聞いているよと姿勢を示すことです。そしてユーモア。あなたがまず、ポジティブであることを確かめましょう。ここが心の戦士の肝心な点です。
だからあなたも大切に、ほどほどに頑張り過ぎないように
あきらめず、あせらず、あわてず、がんばらず、いそがずで・・・・・・・
愛、祈り、謙遜が答えです。
健闘を祈ります。
統合失調症のリハビリテーション(このページの中間部です)⇒
統合失調症の生活技能訓練へ⇒
とは?
よき支えとなるために